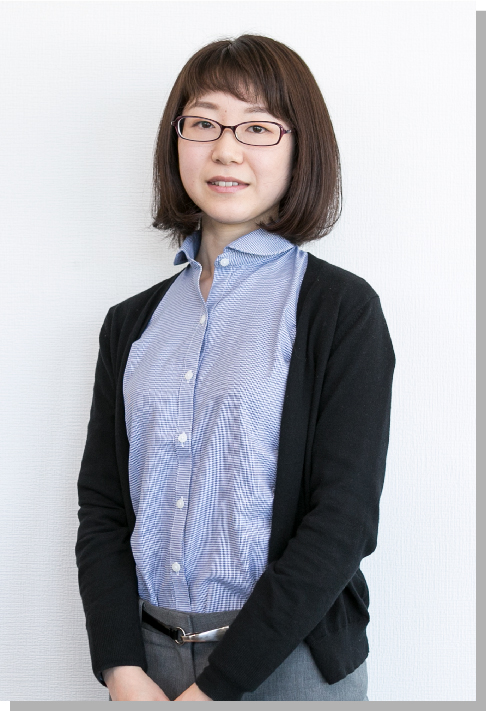学生時代に培った広い視野と
問題解決能力を生かす
- 西日本技術部第1G所属
- 設計担当 / 農業土木(ほ場整備)
- T・N

「今の仕事」について 計画が形になり、発注者から評価をいただけるやりがいのある仕事
入社後は、主にほ場整備業務を担当しています。ほ場業務とは、農地の区画を整え、用排水路や農道、暗渠排水などを整備することで、大型機械の導入や省力化を可能にし、農業の生産性と収益性を高める事業のことをいいます。私は、調査段階から詳細設計に至るまで、用排水施設や農道などハードに関する計画・設計を担当しています。現在は、約130haのほ場整備調査設計業務と、中山間地約13haの実施設計業務を並行して行い、社内のメンバーと連携しながら地元協議や設計作業を進めています。関係者が多い事業のため、わかりやすい資料作成や説明の工夫が不可欠で、作業時間の配分に難しさを感じることがありますが、地元の理解を得られ、計画が形になっていく過程や、発注者から評価をいただいたときには大きなやりがいを感じます。

「BIM/CIMプロジェクトチーム」について ほ場に特化した3Dモデルを作成
通常業務と並行して、2021年からはBIM/CIMプロジェクトチームのメンバーとして、ほ場整備に特化した3Dモデルの作成に取り組んでいます。まだ前例のない業務で、明確なマニュアルもない中、アドバイザーに操作方法を教えてもらいながら試行錯誤を重ねました。通常業務の合間に作業を進めるので、時間的な制約もあります。それでも、南あわじ市のほ場整備調査設計業務では、完成度の高い3Dモデルを作り上げ、業務効率化や情報共有の手助けができました。この取り組みがケーブルテレビで紹介されたこともあり、自分の仕事が形として認められる喜びを感じると同時に、課題解決力を高める貴重な経験になりました。チーム内での意見交換や作業の調整が大切なことや、ヨコの連携力も養われていると感じています。

「成長と目標」について 技術士の資格取得で専門性をさらに高めたい
大学院では、地中レーダ・ドローン測量・酸素同位体比分析などを用いて鳥取砂丘のオアシスの発生消滅メカニズムを研究しました。現在の業務に生かせる技術は少ないのですが、研究を通じて身についた、広い視野と課題解決力は大いに役立っていると感じています。これまでで印象深いのは、水路設計を担当したときのこと。府道を横断する管渠(かんきょ)の計画に際して、他社が実施する地質調査との連携が必要だった案件です。まだ地質を把握する前の段階で、設計に必要な情報を的確に伝えなければならず、上司や他部署にも相談しながら進める中で、多くのことを学びました。今後は、技術士資格を早期に取得し、専門性をさらに高め、発注者や地元関係者から信頼される設計者を目指していきたいと考えています。
ある日のスケジュール
まずはメールチェックから一日がスタート。アシスタントへの作業依頼も行います。ほ場整備業務では、区画整理や水路・農道の計画など、設計検討や図面作成を進めます。午後も引き続きほ場整備の設計業務。発注者や地元の方との打合せに向けた資料を作成し、わかりやすく伝えられるよう工夫します。その後、資料の整理や翌日の段取りを行い、一日を終えます。
| 8:30 | 出社 メールチェック、作業指示等 |
|---|---|
| 9:30 | 設計検討、図面作成等 |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 12:50 | 協議資料作成 |
| 17:20 | 残業(平均1・2時間) |
| 19:00 | 退社 |
私の休日の過ごし方

休日は家族と過ごす時間を大切にしています。平日は子どもたちとゆっくり遊ぶ時間が少ない分、休日は一緒に外出したり遊んだりして過ごしています。子どもたちの笑顔に癒やされ、リフレッシュできる大切な時間です。